「タックルも揃えた。ルアーのサイズ、カラーも充実させた。アクションも工夫した。なのに釣れない――」
わたし自身、そんな悩みに長いことハマっていました。
しかしあるとき気づいたんです。釣果を決める最大の要因は“タックル”ではなく“場所選び”だということに。
この記事では、わたしの釣行の実体験を交えながら、どうすれば釣れる場所にたどり着けるのか?をお伝えします。
同じような悩みを持っている方へ、少しでもヒントになればうれしいです。
「釣れない」のはタックルのせい?
雑誌や動画でプロが使っているタックルを見ると、「これさえあれば釣れるに違いない」と思ってしまいますよね。
しかし、どんなに良いタックルを持っていても、魚のいない場所で釣りをしていてはいつまでたっても釣果は出ません。
場所選びが間違っていると気づかなければ、「ルアーが悪いのかな?」「飛距離が足らない?」「ラインをもっと細く…」とタックルばかりに目が行き試行錯誤、結局今日もボウズという悪循環に陥ります。
もちろん、ルアーのサイズやカラー、ラインの太さ、ロッドやリールの性能を変えることで釣果は上がります。
ただし、それは「魚が釣れる場所」という前提があってこその話です。
もし魚影は濃く、周りの釣り人は釣れているのに自分だけ釣れないのであれば、そこで初めてタックルやアクションを見直せばいい。
それよりもまずは、場所選びに時間とお金を使うことが釣果アップへの近道です。
「釣れる場所」の探し方
釣れる場所には、ちゃんとした理由があります。
潮の流れ、地形、水深、ベイトの存在、過去の実績…。
上手な人が入るポイントには、必ずと言っていいほどそうした「釣れる要素」が揃っています。
では、具体的にどうやって「釣れる場所」を探すのか。
まずは、雑誌やSNSなど、釣り人からの情報をチェックするのが基本です。
加えて、実際に足を運び、人がひっきりなしに訪れる防波堤や、墨跡がびっしり残る防波堤などを自分の目で確かめる方法もあります。
ここからは釣れる場所を見つけるための手段をいくつか紹介します。
- 激戦区:絶えず人が出入りしていて、見つけやすいポイント
- 離島:少しお金と時間はかかるが、好釣果を狙いやすい
- 人脈:釣り仲間が多ければ、穴場に案内してもらえることも
- 通う:同じ場所に通うことで、特定の時季だけ釣れる魚の情報を得られる
それぞれにメリット・デメリットがあり、簡単に見つかって簡単に行ける場所ばかりではありません。
しかし、こうした情報を積み重ねることで、自分だけの「釣れる場所」に近づくことができます。
超有名ポイント「激戦区」
どこの地域にも、必ずと言っていいほど「激戦区」と呼ばれる釣り場があります。
潮通しが良く、ベイトも豊富──いわゆる“好ポイント”の条件がそろっている場所です。
ただし、いつ行っても人が絶えないためプレッシャーが強く、魚はすっかりスレています。場所取り合戦も激しく、隣との距離が近いので投げられる方向も限られます。少しでも移動しようものなら、その隙にすぐ人が入ってくるため、落ち着いてポイントを変えることも難しい。釣り本来の楽しみとは別のところで気を使わなければならず、集中しにくいのも事実です。
それでも「激戦区」にはメリットもあります。
人が多いぶん、何が釣れているのか、時合が来たのかを周囲の様子から判断できますし、情報交換ができることもあります。お互いにタモ入れを手伝ったりと、助け合える場面も多いです。
さらにアクセスの良さも魅力のひとつ。短時間しか釣りができない日でも、さっと立ち寄って竿を出せます。朝マズメ、夕マズメだけ。満潮前後だけ。など、ちょっとだけ釣りたいときには、意外と重宝するポイントです。
離島

アクセスが悪い場所は、たとえ好ポイントの条件がそろっていても人が入りにくく、そのぶん魚影が濃くなります。
特におすすめなのは、橋でつながっている島ではなく、船でしか渡れない島。アクセスが悪ければ悪いほどプレッシャーが少なく、釣果も期待できます。
島へ渡る方法は大きく分けて「渡船」と「定期船」の2つです。
渡船は、釣り人を対象に運航しているため、船長が最新の釣果情報を持っています。釣れる島や好ポイントに直接降ろしてくれ、釣り方のアドバイスまでしてくれます。
「このポイントは潮が沖向きだから流れに乗せて」「今日はこの時間から潮が反転するから、あっちへ移動したほうがいい」といった具合に、細かい情報がもらえるのです。さらに「ここ数日は誰も釣れていない」など、厳しい状況も正直に教えてくれるため、無駄な期待をせずに戦略が立てられます。船長もお客さんに釣ってほしいという気持ちがあるので、渡船で完全なボウズになることはほとんどありません。
また、船長さん以外にも同船する釣り人からの情報も貴重です。出船までの待ち時間に声をかけてもらえたりするので、その時にお互い何を釣りに行くのか、どこの島にいくのか等話したりします。相手の人も渡船をよく利用するので、周辺の島々でどの時季にどの潮で何が釣れるのかというのに詳しい人が多く、本人の実績ベースで情報をもらえるので情報の信頼度が違います。このように渡船を利用することは釣果以外にも情報収集という点で大きなメリットがあります。
定期船は、島民の生活の足として運航されている船で、渡船より安価に利用できます。ただし運航時間は日中が中心で、夜釣りをする場合は夜通しになるのが基本です。ポイントも自分で探す必要がありますが、そのぶん自由度は高く、レンタルサイクルを使って島をランガンすることも可能です。アクセスの悪さゆえ魚のプレッシャーも少なく、驚くほど釣れることも珍しくありません。
定期船も同じ目的の釣り人がいるので声を掛けてもらえる機会が多く、ここでも情報収集ができます。
また、島に渡ってからは島民の人達からも情報収集する機会があります。とくにソロ釣行だと声をかけてもらえることが多く、島内のどこで何が釣れるかという情報にめちゃくちゃ詳しいです。年配の人が多く話し出したら止まりません。一方的に貴重な情報を教えてもらえるので良い思いをすることが多々あります。
どちらの方法も出船時間が決まっているため、必ずしも朝マズメや夕マズメなどの好条件の時間帯に釣りができるとは限りません。ここが、いつでも行ける「激戦区」と大きく異なる点です。
人脈
人脈がある人は、釣れる場所をこっそり教えてもらえたり、一緒に連れて行ってもらえたりします。
そういう場所は、「え?こんなところで釣れるの?」と驚くような意外な場所だったり、自分ひとりでは辿り着けないような場所だったりします。
人脈を築くには、まず信頼関係が必要です。そして、信頼してもらうためには、自分も相手を信頼することが大切です。信頼できる相手には、自分もとっておきの釣り場を教えてあげましょう。そうすることで、お互いに信頼が深まり、相手からも特別な情報を得られるようになります。
人脈を広く持つほど、「釣れる場所」の選択肢はどんどん増えていきます。わたし自身も、人脈から得た情報が釣果への一番の近道になっています。
通う

同じ場所に何度も通っていると、不思議と「ここは釣れる」というポイントに辿り着くことがあります。
時間はかかりますが、季節を追って一年間通い続けていると、ある時季になると特定の魚種が集まり、驚くほど釣れる場所があることに気づきます。
わたしの経験では、そうした場所は「激戦区」と呼ばれる人気ポイントから少し離れた、人がほとんど立ち入らないエリアに多いものです。普段はまったく反応がなくても、条件が揃う時期だけは嘘のようにサクサク釣れるのです。
こうして自分の足で時間をかけて見つけたポイントは、何よりも価値のある“自分だけの釣れる場所”になります。人脈作りにもつながりますが、その情報はむやみに広めず、信頼できる仲間だけにそっと伝えるようにしましょう。
釣れる場所は秘密にしておく
自分で見つけた釣り場や、人から教えてもらったポイントは、むやみに広めないようにするのがマナーです。
釣りの世界では、情報は人づてやSNSを通じて一気に広がってしまいます。
そうなれば、あっという間に人が押し寄せ、せっかくの貴重な場所が荒れてしまうことも珍しくありません。
多くの釣り人は、そのリスクをよく理解しています。だからこそ、本当に信頼できる相手にしか教えないし、教えてもらったときには感謝の気持ちを込めて、自分もとっておきの情報を返すのです。
こうして情報を大切に扱うことが、お互いに良い関係を築き、長く釣りを楽しむ秘訣でもあります。
まとめ|「釣れない」と悩む前に、場所選びを見直してみよう
釣果を伸ばす近道は、最新タックルをそろえることよりも、「どこで釣るか」に時間とお金をかけることでした。
性能の高いロッドやリールも魅力的ですが、同じ道具でも場所が変われば釣果は大きく違います。
自分に合ったスタイルで釣り場を探し、通いやすさや雰囲気も含めて選ぶことで、自然と結果はついてきます。
また、釣り人同士の情報交換や、現場での人付き合いも釣りの醍醐味のひとつ。
道具だけでなく場所選びにも目を向ければ、釣りの世界はもっと広がります。
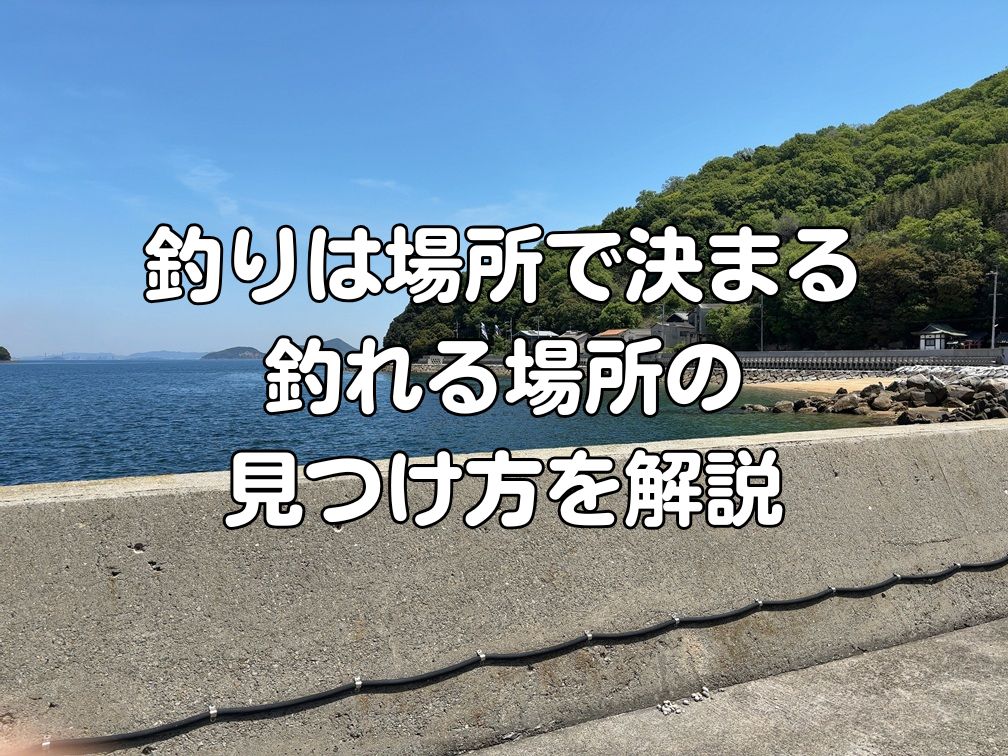
コメント